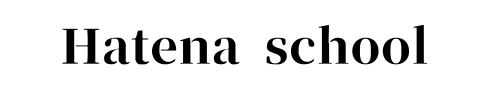朝起きたら体調がすぐれない…。
そんなとき、「会社に休むってどう伝えればいいんだろう?」と悩んだことはありませんか?
英語では、そんな場面でよく使われる便利な表現が “call in” です。
単に「電話する」という意味の call とは違って、call in には「正式に連絡する」というニュアンスがあり、とくに「病欠の連絡」にピッタリ。映画やドラマのセリフにも登場するくらい、ネイティブの日常に根付いた言い方なんです。
この記事では、“call in” の基本的な意味から、映画での使われ方、そして実際にあなたが日常で使えるフレーズ例まで、わかりやすく紹介していきます。
まずは基本から!“call in” の意味を整理しよう
基本の意味
- call → 単に電話をかける行為
- call in → 用件付きの正式な電話(特に病欠や遅刻などの連絡)
“call in” は、「電話で正式に連絡する」という意味で使われます。特に辞典では call in sick(体調不良で休む連絡をする)が代表的な例として紹介されており、call がただの「電話する」なのに対して、call in は「職場や学校に欠勤や遅刻を伝える」といった用件を伴う連絡を表します。
映画や日常会話での意味
映画やドラマでもこのフレーズはそのまま使われ、特に「病欠の連絡」のシーンでよく登場します。
- “I’ll have to call in today.”
(今日は休むので連絡を入れなければならない)
単なる「電話する」ではなく「欠勤を正式に伝える」というニュアンスになります。日常会話でも同様に「体調が悪いから休む」「遅れるから連絡する」といった場面で自然に使える便利な表現です。
実際の例文で “call in” を確認してみよう
call in (職場や学校などに)電話で連絡する

- I’ll call in today because I’m not feeling well.
(体調が悪いので今日は連絡を入れて休む)
- He called in late this morning.
(彼は今朝、遅れると連絡した)
日本語で「電話する」といえば、多くの学習者は phone や call を思い浮かべますよね。もちろん間違いではありません。でも、職場や学校に欠勤・遅刻など、正式な連絡をするときには、call in を使うほうが自然です。
発音をYouGlishで確認しよう!(下のリンクから外部サイトへ移動します)

call in sick / late 病欠・遅刻の連絡をする

- She called in sick this morning.
(彼女は今朝、病欠の連絡をした)
- He called in late because of traffic.
(渋滞のせいで遅刻の連絡をした)
“call in sick” や “call in late” は、ネイティブが実際によく使う 固定表現 です。
特に call in sick は、日常会話からビジネスシーンまで幅広く登場し、「体調不良で欠勤することを職場や学校に連絡する」 という意味で定着しています。たとえば、友達同士の会話で “I called in sick today.” と言えば、「今日は会社に病欠の連絡をした」という自然な表現になります。
一方で call in late は、「遅刻するので連絡する」という意味で、遅れそうなときに会社へ報告する際に使われます。こちらは call in sick ほど頻繁ではありませんが、同じパターンで理解すると覚えやすいです。
発音をYouGlishで確認しよう!(下のリンクから外部サイトへ移動します)
↓call in sick

↓call in late

call in to (番組・会議などに)電話参加する

- Thousands of listeners called in to the radio show.
(何千人ものリスナーがラジオ番組に電話をかけた)
- Please call in to the meeting by 9 a.m.
(9時までに会議に接続してください)
“call in to ” は、テレビやラジオ番組、あるいは会議に「電話や回線を通じて参加する」という意味で使われます。単なる call が「電話する」にとどまるのに対し、call in to は「特定の場に参加する」というニュアンスが加わります。
英語圏では「call-in show」という電話参加型の番組形式があり、このフレーズの使い方を理解すると文化背景も学べます。ビジネスでも「会議に電話で参加する」といった文脈でよく使われる便利な表現です。
発音をYouGlishで確認しよう!(下のリンクから外部サイトへ移動します)

call in on 〜に立ち寄る

- I’ll call in on my parents this weekend.
(今週末、両親の家に立ち寄るよ) - She called in on her grandparents on her way home.
(彼女は帰りに祖父母の家に立ち寄った)
“call in on” は「〜にちょっと立ち寄る」という意味で、特にイギリス英語でよく使われる表現です。アメリカ英語ではあまり耳にせず、その代わりに drop by や stop by が一般的です。ニュアンスとしては「長居せずに、軽く顔を出す」というイメージで、日本語の「ちょっと寄る」「ついでに顔を出す」に近い感覚です。
社交的な響きがあり、visit よりもカジュアルで、drop by より少しだけ丁寧な印象を与えるのも特徴です。イギリスの小説やドラマでは、近所づきあいのシーンや親戚訪問など、日常的な場面で頻繁に見られます。学習者にとっては「イギリス英語らしさ」を感じられる表現の一つと言えるでしょう。
発音をYouGlishで確認しよう!(下のリンクから外部サイトへ移動します)

call + 人・物 + in / call in + 人・物 (人・専門家などを)呼ぶ、招集する

「call + 人/物 + in」と「call in + 人/物」はどちらも「呼ぶ」という意味ですが、ニュアンスや焦点に微妙な違いがあります。以下の例文で違いを見てみましょう。
「call + 人/物 + in」は、誰かを呼び入れたり呼び出したりする動作に焦点を当てた表現です。
例えば、
The manager called me in to discuss the report.
→ マネージャーが私を呼んで報告書について話した。
また、
She called the students in after the break.
→ 休憩後、生徒たちを教室に呼び入れた。
このように「呼ぶ側の動作」に注目しており、その場に入らせる/呼び出すという行為そのものを強調しています。
「call in + 人/物」が外部の専門家や組織など 呼ばれる対象に焦点を当てる のに対して、
「call + 人/物 + in」は 呼ぶ行為そのものに焦点がある のが大きな違いです。
職場で上司が部下をオフィスに呼ぶ場面や、先生が生徒を呼び入れる場面など、日常的なやり取りの中で自然に使われる表現といえます。
発音をYouGlishで確認しよう!(下のリンクから外部サイトへ移動します)

「call in + 人/物」は、外部から人や組織を招集したり、助けを求めたりする場面でよく使われます。
例えば、
The company called in an expert to solve the issue.
→ 会社は問題を解決するために専門家を呼んだ。
また、
The police were called in to control the protest.
→ 抗議を収めるために警察が呼ばれた。
このように「誰を呼ぶのか」という 呼ばれる対象そのものに焦点が当たるのが特徴です。
ニュアンスとしては「外から頼る」イメージが強く、ニュース記事やビジネスの場面で頻繁に登場します。
一方で「call + 人/物 + in」が呼ぶ側の動作を強調するのに対し、
「call in + 人/物」は 呼ばれる側の役割や存在感を際立たせる表現 といえます。
特に、緊急性や専門性が必要な場面で自然に使われるのがポイントです。
発音をYouGlishで確認しよう!(下のリンクから外部サイトへ移動します)

call in a debt/loan 借金・ローンを回収する

- The bank decided to call in the loan after the company missed several payments.
→ その会社が何度も返済を滞らせたため、銀行はローンを回収することにした。
- The court allowed the creditor to call in the outstanding debt immediately.
→ 裁判所は債権者が未払いの借金を即座に回収することを認めた。
“call in a debt” や “call in a loan” は、金融やビジネスの文脈で使われる表現で、「貸し手が借り手に対して、返済期限より前でも借金・ローンの残額を一括請求する」ことを意味します。
通常は、借り手が返済を滞らせたり、信用状況が悪化したときに用いられます。一度この表現が使われると、金融機関は法的措置を取ることもあるため、かなり正式かつ深刻なニュアンスがあります。日常会話で使う機会はまずありませんが、経済ニュース・契約書・ビジネス記事などで見かけることがあります。
発音をYouGlishで確認しよう!(下のリンクから外部サイトへ移動します)
↓call in a loan

↓call in a debt

クイズで確認しよう!
まとめ
英語の学習は、ときに難しく感じることもありますよね。でも一つの表現を掘り下げてみると、「こんなに意味が広がるんだ!」と気づける瞬間があります。今回の call in もそのひとつです。最初は単純に「電話する」と思っていたフレーズが、実は状況によってさまざまな顔を持っていると知ると、英語そのものがぐっと身近に感じられるのではないでしょうか。
大切なのは、すべての意味を一度に暗記することではありません。映画やニュース、日常の会話の中で出会ったときに、「あ、これは前に学んだ“call in”だ!」と気づけること。その積み重ねが、自然に表現を自分のものにしていきます。勉強は単なる作業ではなく、小さな発見や気づきが楽しみに変わる時間です。
もし今日の記事を読んで「使ってみたい」と思ったら、ぜひ身近なシーンで声に出してみてください。口に出すことで記憶に残りやすくなり、実際の会話でもスッと出てくるようになります。学んだフレーズをひとつずつ自分の言葉にしていく過程は、確実にあなたの英語力を育ててくれます。
英語表現の旅はまだまだ続きます。次に出会う新しいフレーズも、きっとあなたの英語をもっと豊かにしてくれるでしょう。楽しみながら、焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう!
今回学んだ表現とあわせて、関連記事もぜひチェックしてみてください👇